厄年
|
男性の厄年
1歳(小厄)
3歳(小厄)
5歳(小厄)
7歳(小厄)
10歳(小厄)
13歳(小厄)
24歳(小厄)
25歳(大厄)
28歳(小厄)
41歳(大厄)
42歳(大厄)
43歳(大厄)
46歳(小厄)
49歳(小厄)
49歳(小厄)
52歳(小厄)
55歳(小厄)
60歳(小厄)
61歳(大厄)
73歳(小厄)
77歳(小厄)
82歳(小厄)
85歳(小厄)
88歳(小厄)
91歳(小厄)
|
女性の厄年
1歳(小厄)
3歳(小厄)
5歳(小厄)
7歳(小厄)
10歳(小厄)
13歳(小厄)
19歳(大厄)
24歳(小厄)
28歳(小厄)
32歳(大厄)
33歳(大厄)
34歳(大厄)
37歳(大厄)
46歳(小厄)
49歳(小厄)
49歳(小厄)
52歳(小厄)
55歳(小厄)
60歳(小厄)
61歳(大厄)
73歳(小厄)
77歳(小厄)
82歳(小厄)
85歳(小厄)
88歳(小厄)
91歳(小厄)
|
厄年は数え年でいう年です。
生まれたその年に一歳、正月に一歳年を重ねるので、2歳になります。
自分の満年+2歳
その年に誕生日がすでに来ていれば+1歳で考えます。
この厄年の中で大厄といわれる歳になった時に、お祓いをする人もいるでしょうけれど、
今では、そういう事さえも忘れられていますよね。
昔は神社とかお寺でお祓いをして、赤飯を炊き、ご近所さんに配ったりして、
厄を少しずつ他人にもらってもらって、厄を軽くしようというおまじない的なことをしていました。
自分の家から一番近い十字路に、厄年の数だけの小銭をまいて、誰かに拾ってもらい、
厄を軽くするというようなことをしていた地域もあります。
私の田舎では、道路では小銭を拾うなと言われていました。
落ちている小銭で厄をもらってしまうからと。
また、お墓でも小銭は拾うなと。
それは、三途の河の渡り賃に、(土葬の時代)棺桶の上にばら撒かれた小銭ですから、
それを拾うとろくなことにならないと言われたものです。
言い伝えですけどね。これ。
でも、何となく説得力があるので、妙な宗教より恐く感じます。
なので、私は道で小銭を拾うことはありません。
拾った時には交番に届けています。(^^)

気をつけてにゃ。

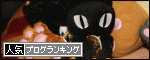
ランキングに参加しています。
ポチッとクリックしていただけると嬉しいです。
PR

